🔰退職後、失業保険等の受給についての悩みをまるっと解決
雇用保険では、失業中の生活を心配しないで新しい仕事を探し、1日も早く再就職できるよう、窓口での職業相談・職業紹介を受けるなどの求職活動を行っていただいた上で、失業等給付を支給しております。
このうち、基本手当(いわゆる通常の失業給付)を受給するに当たっては、ハローワークで以下の手続きをしていただく必要があります。
基本手当とは…
雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、契約期間の満了等により離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。
雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
特に倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者(特定受給資格者といいます。範囲については特定受給資格者の範囲をご覧ください。)及び、特定受給資格者以外の者であって期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職した者(特定理由離職者といい、そのうち「特定理由離職者の範囲」の1に該当する方を指します。)(※補足1)については一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合があります。
※補足1 なお、「特定理由離職者の範囲」の1に該当する方については、受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から令和7年3月31日までの間にある方に限り、所定給付日数が特定受給資格者と同様となります。
(具体的な所定給付日数については、下記枠内をご覧ください。)
公共職業訓練等を受講する場合→訓練中の基本手当の支給、受講手当、通所手当
ハローワークで行う「職業相談」の中で、再就職をするために公共職業訓練等を受講することが必要であると認められた場合は、安定所長がその訓練の受講を「指示」することがあります。この場合には、訓練期間中に所定給付日数が終了しても、訓練が終了する日まで引き続き基本手当が支給されるほか、訓練受講に要する費用として、「受講手当」、「通所手当」などが支給されます。
なお、訓練の受講指示は、原則として所定給付日数内の支給残日数が一定以上ある時点で行うこととしています。
受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の1及び2のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
- ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。- 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
- 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
- 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
- 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
 注意船員の方が引き続き船員の求人を希望する場合は地方運輸局で求職の申込みと雇用保険の給付の手続きを行っていただくこととなります。このような場合は以下「ハローワーク」とあるのを「地方運輸局」となりますのでご留意ください。
注意船員の方が引き続き船員の求人を希望する場合は地方運輸局で求職の申込みと雇用保険の給付の手続きを行っていただくこととなります。このような場合は以下「ハローワーク」とあるのを「地方運輸局」となりますのでご留意ください。 - 離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。 ※補足2 被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上又は賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上ある月を1か月と計算します。
受給期間
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。
この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日以降、早期に申請していただくことが原則ですが、延長後の受給期間の最後の日までの間であれば、申請は可能です。住所又は居所を管轄するハローワークに申請してください。(代理人又は郵送でも結構です。)
※ なお、再就職手当受給後に倒産等により再離職した者については、一定期間受給期間が延長される場合があります。
離職日の翌日以後に事業を開始等した方(事業を開始した方・事業に専念し始めた方・事業の準備に専念し始めた方)が事業を行っている期間等は、下記の要件を満たす場合、最大3年間受給期間に算入しない特例を申請できます。
事業の実施期間が30日以上であること。
「事業を開始した日」「事業に専念し始めた日」「事業の準備に専念し始めた日」のいずれかから起算して30日を経過する日が受給期間の末日以前であること。
当該事業について、就業手当または再就職手当の支給を受けていないこと。
当該事業により自立することができないと認められる事業ではないこと。
※次のいずれかの場合は、に該当します。
・雇用保険被保険者資格を取得する者を雇い入れ、雇用保険適用事業の事業主となること。
・登記事項証明書、開業届の写し、事業許可証等の客観的資料で、事業の開始、事業内容と事業所の実在が確認できること。
離職日の翌日以後に開始した事業であること。
※離職日以前に当該事業を開始し、離職日の翌日以後に当該事業に専念する場合を含みます。
この特例を受けようとする場合は、事業を開始した日・事業に専念し始めた日・事業の準備に専念し始めた日の翌日から2か月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに申請する必要があります。(代理人又は郵送でも結構です。)
※ ただし、就業手当または再就職手当を支給申請し、不支給となった場合は、この期間を超えてもこれらの手当の支給申請日を特例の申請日として受給期間の特例を申請できます。
不正受給
偽りその他不正の行為で基本手当等を受けたり、又は受けようとした場合には、以後これらの基本手当等を受けることができなくなるほか、その返還を命ぜられます。
更に、原則として、返還を命じた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命ぜられることとなります。
支給額
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(令和6年8月1日現在)
| 30歳未満 | 7,065円 |
|---|---|
| 30歳以上45歳未満 | 7,845円 |
| 45歳以上60歳未満 | 8,635円 |
| 60歳以上65歳未満 | 7,420円 |
技能習得手当について
技能習得手当とは、受給資格者が積極的に公共職業訓練等を受ける条件を整え、その再就職を促進するため、受給資格者が公共職業安定所長又は地方運輸局長の指示により公共職業訓練等を受講する場合に基本手当とは別に受けられるものです。
技能習得手当には以下のとおり、受講手当と通所手当の二種類があります。
受講手当について
受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に支給されます。支給の対象となるのは、基本手当の支給の対象となる日のうち公共職業訓練等を受けた日です。
受講手当の日額は500円です。
受講手当の上限額は20,000円です。
通所手当について
通所手当は、受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設へ通所するために交通機関、自動車等を利用する場合に支給されます。
通所手当の月額は通所方法によりますが、最高42,500円までです。
支給対象にならない日がある月については日割により減額して支給されます。
技能習得手当の受給手続
技能習得手当の受給資格者は、公共職業安定所長の指示により公共職業訓練等を受けることになったとき、すみやかに、「公共職業訓練等受講届」及び「公共職業訓練等通所届」に受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所長に提出します。
技能習得手当の支給を受けるためには、上記の手続きをした上で失業認定の日に公共職業訓練等受講証明書に受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所に提出することが必要です。
寄宿手当について
寄宿手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために、家族(その者により生計を維持されている同居の親族※補足3)と別居して寄宿する場合に支給されます。
対象となる期間は公共職業訓練等を受けている期間のうち上記家族と別居して寄宿していた期間です。寄宿手当の月額は10,700円です。
受給資格者が家族と別居して寄宿していない日等、支給対象とならない日がある月については日割により減額して支給されます。
※補足3 婚姻の届出はしていないが事実上その者と婚姻と同様の事情にある者を含みます。
寄宿手当の受給手続
受給資格者は公共職業安定所長の指示により公共職業訓練等を受けることになったとき、すみやかに、「公共職業訓練等受講届」及び「公共職業訓練等通所届」に受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所長に提出します。
寄宿手当の支給を受けるためには、上記の手続きをした上で失業認定の日に公共職業訓練等受講証明書に受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所に提出することが必要です。
傷病手当について
傷病手当とは、受給資格者が離職後、公共職業安定所に来所し、求職の申込みをした後に15日以上引き続いて疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、その疾病又は負傷のために基本給付の支給を受けることができない日の生活の安定を図るために支給されるものです。
(14日以内の疾病又は負傷の場合には基本手当が支給されます。)
傷病手当の日額は基本手当の日額と同額です。
30日以上引き続いて疾病又は負傷のために職業に就くことができないとき
受給資格者の申出によって、基本手当の受給期間を最大4年間まで延長できます。
受給期間を延長した後、その延長理由と同様の疾病又は負傷を理由として傷病手当の支給を申請したときの支給日数は、その受給期間の延長がないものとした場合における支給できる日数が限度となります。
※ 疾病又は負傷について他の法令により行われる類似の給付を受ける日については支給されません。
傷病手当の受給手続
職業に就くことができない理由がやんだ後における最初の認定日までに居住地を管轄する公共職業安定所で傷病の認定を受けなければなりません。
なお、傷病手当支給申請書は本人以外の代理人による提出又は郵送によっても差し支えありません。
高年齢求職者給付金について
高年齢被保険者(※補足4)が失業した場合、一般の被保険者の場合と異なり、被保険者であった期間に応じ基本手当日額の30日分又は50日分に相当する高年齢求職者給付が支給されます。
※補足4 高年齢被保険者とは、65歳以上の被保険者であって、短期雇用特例被保険者や日雇労働被保険者とならない方をいいます。
高年齢求職者給付金の受給要件について
高年齢被保険者が高年齢求職者給付金の支給を受けるには、住居地を管轄する公共職業安定所に来所し、求職の申し込みをしたうえ、高年齢受給資格の決定を受けなければなりません。
この決定において高年齢受給資格が認められるには高年齢被保険者であって以下の要件を満たす場合に限られます。
- 離職により資格の確認を受けたこと。
- 労働の意志及び能力があるにもかかわらず職業に就くことができない状態にあること。
- 算定対象期間(原則は離職前1年間)に被保険者期間が通算して6か月以上あること。
※ 被保険者期間の計算方法は一般の被保険者と同様です。
高年齢求職者給付金の支給について
高年齢求職者給付金は失業認定を行った日に支給決定されます。
失業認定は一般の受給資格者の場合とは異なり1回限りです。
支給額は、被保険者であった期間に応じて次の表に定める日数分の基本手当の額(※補足5)に相当する額とされています。
| 被保険者であった期間 | 高年齢求職者給付金の額 |
|---|---|
| 1年以上 | 50日分 |
| 1年未満 | 30日分 |
※補足5 基本手当日額は、被保険者期間として計算された離職前の6か月間に支払われた賃金を基礎として計算されます。
特例一時金について
特例一時金とは、季節的に雇用されている者等を短期雇用特例被保険者として、一般の被保険者と区別して給付されるものです。このような一時金制度をとっているのは、これらの短期雇用特例被保険者は一定の期間ごとに就職と離職を繰り返すため、一般の被保険者への求職者給付より一時金制度とすることのほうがその生活実態により即しているからです。
特例一時金の受給要件について
短期雇用特例被保険者が特例一時金の支給を受けるには、住居所を管轄する公共職業安定所に来所し求職の申し込みをした上で、特例受給資格の決定を受けなければなりません。
その決定において特例受給資格が認められるには、短期雇用特例被保険者であって以下の要件を満たす者に限られます。
- 離職により資格の確認を受けたこと。
- 労働の意思及び能力があるにもかかわらず職業に就くことができない状態にあること。
- 算定対象期間(原則は離職前1年間)に被保険者期間が通算して6か月以上あること。 ※ 被保険者期間の計算は一般の被保険者、又は高年齢被保険者と異なり、一歴月中に賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上又は賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上ある月を被保険者期間1か月として計算します。
特例一時金の支給について
特例一時金の支給は失業認定を行った日に行われます。
特例一時金の額は特例受給資格者を一般被保険者とみなして計算した基本手当の日額の30日分とされています(ただし、当分の間は暫定措置で40日分となります)。
ただし、失業認定があった日から受給期限日(※補足6)までの日数が30日(ただし当分の間は暫定措置で40日)未満であるときは特例一時金の額はその日数分となります。
※補足6 離職の日の翌日から起算して6か月後の日
日雇労働求職者給付金について
雇用保険では、日雇労働被保険者について、一般被保険者とは異なる制度を設け、日雇労働被保険者が失業した場合には、その雇用形態に即した求職者給付を支給することとしています。
日雇労働被保険者について
日雇労働者とは、日々雇い入れられる者及び30日以内の期間を定めて雇い入れられる者のことをいいます。
日雇労働者のうち、下記の要件のいずれかに該当する者が日雇労働被保険者になります。
- 適用区域(特別区もしくは公共職業安定所の所在する市町村の区域(厚生労働大臣が指定する区域は除かれます。)または厚生労働大臣が指定する隣接市町村の全部または一部の区域。)内に居住し、適用事業に雇用される者
- 適用区域外に居住し、適用区域内の適用事業に雇用される者
- 適用区域外に居住し、適用区域外の適用事業で、日雇労働の労働市場の状況その他の事情に基づき厚生労働大臣が指定したものに雇用される者
上記1~3に該当しない日雇労働者であっても、適用事業に雇用される場合は、その者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所長の許可を受けて被保険者となることができます
※ なお、直前2か月の各月に同一事業主に18日以上雇用された場合及び同一事業主に継続して31日以上雇用された場合は、原則として、一般保険者として取り扱われます。
上記要件に該当する日雇労働者は、その要件に該当するに至った日から5日以内に居住地を管轄する公共職業安定所長に届出をしなければなりません。この届出によって公共職業安定所長から日雇労働の実態があるなど日雇労働被保険者であると確認された場合には、日雇労働被保険者手帳が交付されます。
日雇労働被保険者について
失業した日雇労働被保険者は、失業の日の属する月の前2月において通算して26日分以上の印紙保険料が納付されている場合(※補足7)に、公共職業安定所において失業認定を行った上で、日雇労働求職者給付金が支給されます。
※補足7 日雇労働被保険者は事業主に使用されたときはその都度、雇用保険印紙の貼付を受けるために、所持する日雇労働被保険者手帳を事業主に提出しなければなりません。事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合には、その者に賃金を支払う都度、その使用した日数に相当する枚数の雇用保険印紙をその使用した日の被保険者手帳における該当日欄にはり、消印しなければなりません。
給付金の日額は直前2か月の手帳に貼付された雇用保険印紙の枚数等により定められています
その月に支給できる日数の上限は、直前2か月の手帳に貼付された雇用保険印紙の枚数により13日から17日までの範囲で定められています。
《ご質問等につきましては、お手数ですが、最寄りのハローワークまでお願いいたします。》
雇用保険の具体的な手続き
雇用保険の具体的な手続き①離職
できれば在職中に「雇用保険被保険者証」の有無を確認してください。また、会社がハローワークに提出する「離職証明書」については、離職前に本人が氏名の記載をすることになっていますので、離職理由等の記載内容についても確認してください。離職後、「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」が届きます(受取りに行く場合もあります)。
なお、会社から離職票が交付されない場合や、事業主が行方不明の場合等については、住居地を管轄するハローワークにお問い合わせください。
雇用保険の具体的な手続き②受給資格の決定
住居を管轄するハローワークに行き、「求職の申込み」を行ったのち、「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」を提出します。
雇用保険の手続きは、月曜日~金曜日(休祝日・年末年始を除く)の8時30分~17時15分です。また、「受給資格決定」の他に「求職の申込み」の手続きもあり、求職申込みには一定の時間がかかること等から、16時前までのご来所をお勧めさせていただきます。
以下の書類が必要ですので持参してください。
- 雇用保険被保険者離職票(-1、2)
- 個人番号確認書類(いずれか1種類) マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票(住民票記載事項証明書)
- 身元(実在)確認書類((1)のうちいずれか1種類((1)の書類をお持ちでない方は、(2)のうち異なる2種類(コピー不可)) (1)運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、官公署が発行した身分証明書・資格証明書(写真付き)など (2)公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書など
- 写真(最近の写真、正面上三分身、縦3.0cm×横2.4cm)2枚 ※ 本手続及びこれに続き今後行う支給申請ごとに個人番号カード(マイナンバーカード)を提示することで省略が可能です。
- 本人名義の預金通帳又はキャッシュカード(一部指定できない金融機関があります。ゆうちょ銀行は可能です。)
ハローワークでは、受給要件を満たしていることを確認した上で、受給資格の決定を行ないます。このときに、離職理由についても判定します。
なお、離職理由に異議がある場合(実際は、事業主からの退職勧奨であるにも関わらず、自己都合退職とされている場合など)は、ハローワークにご相談ください。
ハローワークにおいて、事実関係を調査のうえ、離職理由を判定します。
雇用保険の具体的な手続き③雇用保険受給者初回説明会
指定の日時に開催されますので、必ず出席してください。
「雇用保険受給資格者のしおり」、筆記用具等を持参してください。
受給説明会では、雇用保険の受給について重要な事項の説明を行いますので、説明をよく聞いて、制度を十分理解してください。
また、「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」をお渡しし、第一回目の「失業認定日」をお知らせします。
雇用保険の具体的な手続き④失業の認定
原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。
指定された日に管轄のハローワークに行き、「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。
雇用保険の具体的な手続き⑤基本手当の支給を受けるためには
失業の認定を受けようとする期間(認定対象期間。原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間)中に、原則として2回以上(基本手当の支給に係る最初の認定日における認定対象期間中は1回)の求職活動(就職しようとする意思を具体的かつ客観的に確認できる積極的な活動のことをいいます。)の実績が必要となります。
また、自己都合などで退職された場合、離職理由によっては、待期期間満了後2か月間(過去5年間に2回以上自己都合で離職している場合3か月間)は基本手当が支給されません(離職理由による給付制限)が、この期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間については、原則として2回以上(給付制限期間が3か月の場合は、原則として3回以上)の求職活動の実績が必要となります。
雇用保険の具体的な手続き⑥求職活動の範囲
求職活動の範囲(主なもの)は、次のとおりであり、単なる、ハローワーク、新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧、単なる知人への紹介依頼だけでは、この求職活動の範囲には含まれません。
- 求人への応募
- ハローワークが行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、各種講習、セミナーの受講など
- 許可・届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、求職活動方法等を指導するセミナー等の受講など
- 公的機関等((独)高齢・障害・求職者雇用支援機構、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施する職業相談等を受けたこと、各種講習・セミナー、個別相談ができる企業説明会等の受講、参加など
- 再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験
※ 公共職業訓練等の受講期間中や、採否通知を待っている間など、上記の求職活動実績を必要としない場合があります。
※ 求職活動の実績については、利用した機関等への問い合わせ等により、ハローワークが事実確認を行うことがあります。
※ 求職の申込み後の、失業の状態にある7日間は、基本手当は支給されません。
これを「待期」といいます。
雇用保険の具体的な手続き⑦受給
失業の認定を行った日から通常5営業日で、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。
(ただし、休祝日又は年末年始(12月29日~1月3日)を含む場合は、遅れる場合があります。)
再就職が決まるまでの間、所定給付日数(基本手当が支給される最高日数)を限度として、「失業の認定」、「受給」を繰り返しながら仕事を探すことができます。
所定給付日数は、離職理由、離職時の年齢、被保険者であった期間等によって異なります。
住居所を管轄するハローワーク以外での求職活動を希望する場合は、当該希望地を管轄するハローワークで手続きが可能な場合があります。詳しくは、お近くの都道府県労働局、ハローワークにお尋ねください。
なお、基本手当を受けられる期間は、原則として離職の翌日から1年間です。
(これを過ぎると、所定給付日数の範囲内であっても基本手当が受けられませんので、ご注意ください)。
就職促進給付
雇用保険の失業等給付の就職促進給付のうち「就業促進手当」として、「再就職手当」、「就業促進定着手当」、「就業手当」などがあります。
その概要は以下のとおりです。
再就職手当について
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。支給額は、所定給付日数の支給残日数×給付率×基本手当日額((注意1) 一定の上限あり)となります。
給付率については以下のとおりとなります。
- 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×70%×基本手当日額((注意1)一定の上限あり)。
- 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額((注意1)一定の上限あり)。
 注意事項
注意事項
| 注意1: | 基本手当日額の上限は、6,395円(60歳以上65歳未満は5,170円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。) |
詳しくは再就職手当のご案内[PDF:2744KB]をご覧ください。
就業促進定着手当について
就業促進定着手当は、再就職手当の支給を受けた人が、引き続きその再就職先に6か月以上雇用され、かつ再就職先で6か月の間に支払われた賃金の1日分の額が雇用保険の給付を受ける離職前の賃金の1日分の額(賃金日額)に比べて低下している場合、就業促進定着手当の給付を受けることが出来ます。
支給額は、(離職前の賃金日額-再就職手当の支給を受けた再就職の日から6か月間に支払われた賃金額の1日分の額)×再就職の日から6か月間内における賃金の支払いの基礎となった日数(通常月給制の場合は暦日数、日給月給制の場合はその基礎となる日数、日給制や時給制の場合は労働の日数)となります。
ただし、次のとおり上限額があります。
上限額:基本手当日額(注意2)×基本手当の支給残日数に相当する日数(注意3)× 40%(注意4)
 注意事項
注意事項
| 注意2: | 基本手当日額の上限は、6,395円(60歳以上65歳未満は5,170円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。) |
| 注意3: | 再就職手当の給付を受ける前の支給残日数です。 |
| 注意4: | 再就職手当の給付率が70%の場合は、30%です。令和7年4月1日以降に再就職手当の支給に係る再就職をした場合は、再就職手当の給付率に関係なく20%です。 |
詳しくは再就職後の賃金が、離職前の賃金より低い場合には、「就業促進定着手当」が受けられます [PDF:186KB]をご覧ください。
就業手当について
就業手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。支給額は、就業日×30%×基本手当日額((注意5)一定の上限あり)となります。
なお、就業手当は、令和7年3月31日をもって廃止されます。令和7年4月1日以降に支給要件を満たす方については、支給されません。
 注意事項
注意事項
| 注意5: | 1日当たりの支給額の上限は、1,918円(60歳以上65歳未満は1,551円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。) |
常用就職支度手当
常用就職支度手当は、基本手当の受給資格がある方(基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満である方に限ります。)、高年齢受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者のうち、障害のある方など就職が困難な方が安定した職業に就いた場合に、一定の要件に該当すると支給されます。
支給額は、90(原則として基本手当の支給残日数が90日未満である場合には、支給残日数に相当する数(その数が45を下回る場合は45))×40%×基本手当日額((注意6) 一定の上限あり)となります。
 注意事項
注意事項
| 注意6: | 基本手当日額の上限は、6,395円(60歳以上65歳未満は5,170円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。) |
移転費について
受給資格者等がハローワーク、特定地方公共団体または職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又はハローワークの所長の指示した公共職業訓練等を受講するため、その住所又は居所を変更する必要がある場合に、受給資格者本人とその家族(その者により生計を維持されている同居の親族)の移転に要する費用が支給されます。
移転費の受給要件について
移転費の支給を受けるには以下の要件を満たしていることが必要です。
- 雇用保険の受給資格者等であること。
- 待期の期間が経過した後に就職し、または公共職業訓練等を受けることとなったこと。
- ハローワーク、特定地方公共団体または職業紹介事業者(注意7)が紹介した職業(注意8)に就くため、またはハローワークの所長の指示した公共職業訓練等を受けるために、住所・居所を変更すること。
- 事業所または訓練施設が、次のいずれかに該当するため、ハローワークが住所・居所の変更が必要であると認めること。 (1) 通勤(所)時間が往復4時間以上であること (2) 交通機関の始(終)発の便が悪く、通勤(所)に著しい障害がある場合 (3) 移転先の事業所・訓練施設が、特殊性や事業主の要求によって移転を余儀なくされる場合
- その就職について、就職準備金その他移転に要する費用が就職先から支給されないこと、又は就職先からの支給額が移転のために実際に支払った費用に満たないこと。
※ 上記のほか、職業紹介の拒否等による給付制限を受けた場合は、その給付制限期間が経過した後に、就職し、または公共職業訓練等を受けることとなったことが必要です。
 注意事項
注意事項
| 注意7: | 職業安定法第4条第8項に規定する特定地方公共団体または職業安定法第18条の2に規定する職業紹介事業者をいいます。なお、職業紹介事業の停止を命じられている職業紹介事業者または業務改善命令を受けている職業紹介事業者から紹介を受けた場合は、移転費の支給対象とはなりません。 |
| 注意8: | 雇用期間が1年未満である場合や、循環的に雇用されることが慣行となっている場合を除きます |
移転費の支給について
移転費には、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、移転料、着後手当の6種類があります。
移転費の支給を受けることができるもの及びその者が随伴する家族について、その旧居住地から、新居住地までの区間の順路によって計算した額が支給されます。
移転費の支給を受けようとする受給資格者等
移転の日の翌日から起算して1か月以内に住居所管轄のハローワークへ、移転費支給申請書に受給資格者証等を添えて提出する必要があります。
移転費の支給を受けた受給資格者等
移転後すぐ、就職先の事業主に、移転費支給決定書を提出します。
就職先の事業主は、その移転費支給決定書に基づき移転証明書を作成し、移転費を支給したハローワークへ送付します。
移転費の支給を受けた受給資格者等が、紹介された職業に就かなかったとき、指示された公共職業訓練等を受けなかったとき、又は移転しなかったとき、その支給された移転費に相当する額を返還しなければなりません。
広域求職活動費について
広域求職活動費とは、受給資格者等がハローワークの紹介により遠隔地にある求人事業所を訪問して求人者と面接等をした場合支払われるもので、交通費及び宿泊料が支給されます。
広域求職活動費の受給要件について
受給資格者等が広域求職活動費の支給を受けるためには以下の要件を満たすことが必要です。
- 雇用保険の受給資格者等であること。
- 待期の期間が経過した後に広域求職活動を開始したこと。
- ハローワークに紹介された求人が、その受給資格者の方に適当と認められる管轄区域外に所在する事業所のもので、その事業所の常用求人であること。
- 住居所管轄のハローワークから、訪問する求人事業所の所在地を管轄するハローワークの間の距離(往復)が、交通費計算の基礎となる鉄道等の距離で200キロメートル以上あること。
- 広域求職活動に要する費用が、訪問先の事業所の事業主から支給されないこと、又はその支給額が広域求職活動費の額に満たないこと。
※ 上記のほか、職業紹介の拒否等による給付制限を受けた場合は、その給付制限期間が経過した後に、広域求職活動を開始したことが必要です。
広域求職活動費の支給について
交通費については、住居所管轄のハローワークの所在地から訪問する事業所の所在地を管轄するハローワークの所在地までの順路について、通常の経路及び方法により、移転費の場合に応じて計算した額が支給されます。
宿泊費については、交通費計算の基礎となる距離と、訪問する事業所の数に応じて定められています。
広域求職活動費の支給を受けようとする受給資格者等は、広域求職活動を終了した日の翌日から10日以内に、住居所管轄のハローワークへ、求職活動支援費(広域求職活動費)支給申請書に受給資格者証、広域求職活動指示書及び広域求職活動面接等訪問証明書を添えて提出します。
短期訓練受講費について
受給資格者等が平成29年1月以降に、ハローワークの職業指導により再就職のために必要な職業に関する教育訓練を受け、当該訓練を修了した場合に、本人が訓練受講のために支払った教育訓練経費(注意9)の2割(上限10万円、下限なし)が支給される制度です。
 注意事項
注意事項
| 注意9: | 教育訓練経費とは、入学料(入学金又は登録料)と受講料であり、教育訓練施設が証明する額です。 |
短期訓練受講費の受給要件について
短期訓練受講費の支給を受けるには以下の要件を満たしていることが必要です。
- 教育訓練(注意10)を受講する前に、その訓練を受けるためのハローワークの職業指導(以下「受講指導」と言います。)を受けていること。
- 受講指導を受ける日において、受給資格者等であること。
- 待期の期間が経過した後に教育訓練の受講を開始したこと。
 注意事項
注意事項
| 注意10: | 支給対象となる教育訓練 |
| (1) 一般教育訓練給付の対象講座を実施している教育訓練実施者が実施していること。 (2) 公的職業資格の取得を目標とする1か月未満の教育訓練であること。 (3) 一般教育訓練給付の対象講座として指定されていないこと。 (ただし、一般教育訓練給付の講座指定を受けている場合であっても、一般教育訓練給付の支給要件を満たさない者が受講した場合は対象となります。) (4) 教育訓練の開始時期、内容、対象者、目標及び修了基準が明確であり、教育訓練実施者が、その訓練について、適切に受講されたことを確認し、修了させるものであること。 | |
短期訓練受講費の支給について
本人が訓練受講のために支払った教育訓練経費の2割(上限10万円、下限なし)が支給されます。
受講開始前に行う手続き
短期訓練の受講を希望する場合は、必ず受講開始前に、以下(1)~(3)の手続きを行った上で、教育訓練を受講する必要があります。
(1) 短期訓練受講費支給要件照会票の提出
受給資格があることを確認するため、住居所管轄のハローワークの雇用保険窓口へ教育訓練実施者の証明を受けた「短期訓練受講費支給要件照会票」を提出します。
※ 「短期訓練受講費支給要件照会票」は、ハローワークの雇用保険窓口で交付していますので、必要な場合は、ハローワークの雇用保険窓口にお申し出下さい。
(2) 短期訓練受講費支給要件回答書の受理
住居所管轄のハローワークから交付された「短期訓練受講費支給要件回答書」に「支給要件を満たしています。」と記載されていた場合のみ(3)の受講指導を受けられます。
(3) ハローワークによる受講指導
住居所管轄のハローワークの職業相談窓口に「短期訓練受講費支給要件回答書」を持参し、受講指導を受けます。ハローワークでは、教育訓練の受講が再就職のために必要かどうかなどを確認し、「短期訓練受講指導書」を交付します。
受講修了後に行う手続き
「求職活動支援費(短期訓練受講費)支給申請書」に必要書類を添えて、教育訓練の修了日の翌日から1か月以内に住居所管轄のハローワークへ提出してください。
求職活動関係役務利用費について
求職活動関係役務利用費は、受給資格者等が平成29年1月以降に求人者との面接等をしたり、教育訓練を受講するため、子について保育等サービス(注意11)を利用した場合に、保育等サービスの利用のために本人が負担した費用(注意12)の一部(上限額あり)が支給される制度です。
 注意事項
注意事項
| 注意11: | 認可保育所の保育、認可幼稚園の保育、認定子ども園の保育、一時預かり事業等を言います。 |
| 注意12: | 費用とは、保育等サービス実施者に対して支払った利用料として、保育等サービス実施者が証明する額(消費税込み)です。 |
求職活動関係役務利用費の受給要件について
求職活動関係役務利用費の支給を受けるためには以下の要件を満たすことが必要です。
- 保育等サービスを利用した日において受給資格者等であること。
- 待期の期間が経過した後に保育等サービスを利用したこと。 ※ 待期の期間が経過する前に保育等サービスの利用を開始した場合は、待期の期間が経過した後の保育等サービスの利用分のみ支給対象となります。
- 対象となる面接等、教育訓練 (1) 求人者との面接等 求人者との面接等とは、求人者との面接のほか、筆記試験の受験、ハローワーク、許可・届出のある職業紹介事業者等が行う職業相談、職業紹介等、公的機関等が行う求職活動に関する指導、個別相談が可能な企業説明会等、失業認定における求職活動に該当する活動であること。 (2) 教育訓練の受講 教育訓練の受講とは、ハローワークの指示・推薦により公共職業訓練等を受講する場合、就職支援計画に基づき求職者支援訓練を受講する場合、ハローワークの指導により各種養成施設に入校する場合、教育訓練給付の対象訓練及び短期訓練受講費の対象訓練等を受講している場合であること。
- 対象となる子(年齢制限なし) (1) 法律上の親子関係に基づく子(実子の他養子も含む。) (2) 特別養子縁組を成立させるために監護を受けている者 (3) 養子縁組里親に委託されている者、養育里親に委託されている者
求職活動関係役務利用費の支給について
- 支給額 保育等サービス利用のために本人が負担した費用(保育等サービス利用費)の80%が支給(1日あたりの支給上限額6,400円)されます。
- 保育等サービス利用費の算出方法 (1) 日払いの場合 面接等、教育訓練を受けた日に要した利用費を1日単位で申請 (2) 月額の場合 『月額費用÷その月の暦日数×面接等や教育訓練を受けた日数』で算出した額を申請
- 支給対象となる上限日数 (1) 求人者と面接等をした日 ⇒ 『15日』 (2) 対象訓練を受講した日 ⇒ 『60日』 ※ (1)及び(2)のいずれも上限日数に達するまでは、支給対象となります。
求職活動関係役務利用費の支給を受けようとする受給資格者等は、「求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)支給申請書」に、下記の必要書類を失業の認定日に住居所管轄のハローワークへ提出を行う必要があります。(ただし、ハローワークの指示により公共職業訓練等を受講する受給資格者(証明認定を希望する方に限ります。)は、失業の認定の対象となる月分について、翌暦月中に提出を行う必要があります。)
必要書類
- 受給資格者証等
- 保育等サービス事業者が発行する保育等サービス費用に係る領収書
- 保育等サービス事業者が発行する「保育等サービス利用証明書(求職活動関係役務利用費)」
- 保育等サービス事業者が発行する「返還金明細書」(領収書を発行後、利用料の値引き等により、保育等サービス利用費の一部が返還された場合に限ります。)
- 事業主の証明を受けた「面接等求職活動証明書(求職活動関係役務利用費) 」等の求人者との面接等を行ったことを証明する書類(求人者と面接等を行った場合に限ります。)
- 訓練実施者の証明を受けた「訓練等受講証明書(求職活動関係役務利用費)」等の訓練を受講したことを証明する書類(教育訓練を受講した場合に限ります。)
- 対象となる子の氏名、本人との続柄を確認できる住民票記載事項証明書等
- 保育等サービス利用費について、地方公共団体等の第3者から補助を受けた場合は、その額を証明する書類
《ご質問等につきましては、お手数ですが、最寄りのハローワークまでお願いいたします。》
申請期限を過ぎたことにより、雇用保険の給付を受けられなかった方は、こちら をご覧ください
をご覧ください
よくある質問
失業保険の失業とはどんな状態?
「失業」とは、離職した方が、「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことをいいます。したがって、次のような状態にあるときは、失業給付を受けることができません。
- 病気やけがのために、すぐには就職できないとき
- 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
- 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
- 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
失業保険の不正受給ってどんな場合があるの?
本来は、基本手当を受けられないにもかかわらず、虚偽の申告などにより基本手当の支給を受けようとした場合には、不正受給としてそれ以後の支給がすべて停止され、厳しい処分が行われます(他の給付も同様です。)。
次のようなことは、絶対に行わないようにしてください。
- 求職活動の実績がないにもかかわらず、失業認定申告書にその実績について虚偽の申告をする。
- 就職や就労(パート、アルバイト、日雇、試用期間なども含みます。)をし、また、自営を開始した場合に、そのことを失業認定申告書で 申告しない。
- 内職や手伝いをした事実や収入を隠したり、偽った申告をする。
- 実際には行っていない求職活動を、「失業認定申告書」に実績として記すなど偽りの申告を行った場合
- 就職や就労(パートタイマー、アルバイト、派遣就業、試用期間、研修期間、日雇などを含む。)したにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さず、偽りの申告を行った場合
- 自営や請負により事業を始めているにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さず、偽りの申告を行った場合
- 内職や手伝いをした事実及びその収入を「失業認定申告書」に記さず、偽りの申告を行った場合
- 会社の役員に就任(名義だけの場合も含む。)しているにもかかわらず、「失業認定申告書」に記さず、偽りの申告を行った場合
- 定年後、「積極的に就職しようとする気持ち」や「いつでも就職できる能力(身体的・環境的)」がなく、しばらく失業給付を受け、受給終了直後に年金を受給しようと考えている者が、「失業認定申告書」により偽りの申告を行った場合
こういった不正行為が行われた場合、その不正行為があった日以降の日について、基本手当等が一切支給されず、不正に受給した基本手当等の相当額(不正受給金額)の返還が命ぜられます。さらに、返還が命ぜられた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付(いわゆる「3倍返し」)が命ぜられることとなります。
したがって、安定所に提出する書類には事実をありのままに記入し、不正に雇用保険を受給することのないようにしてください。

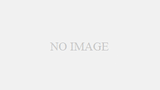
コメント